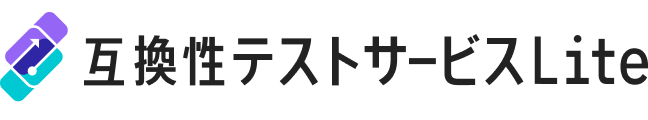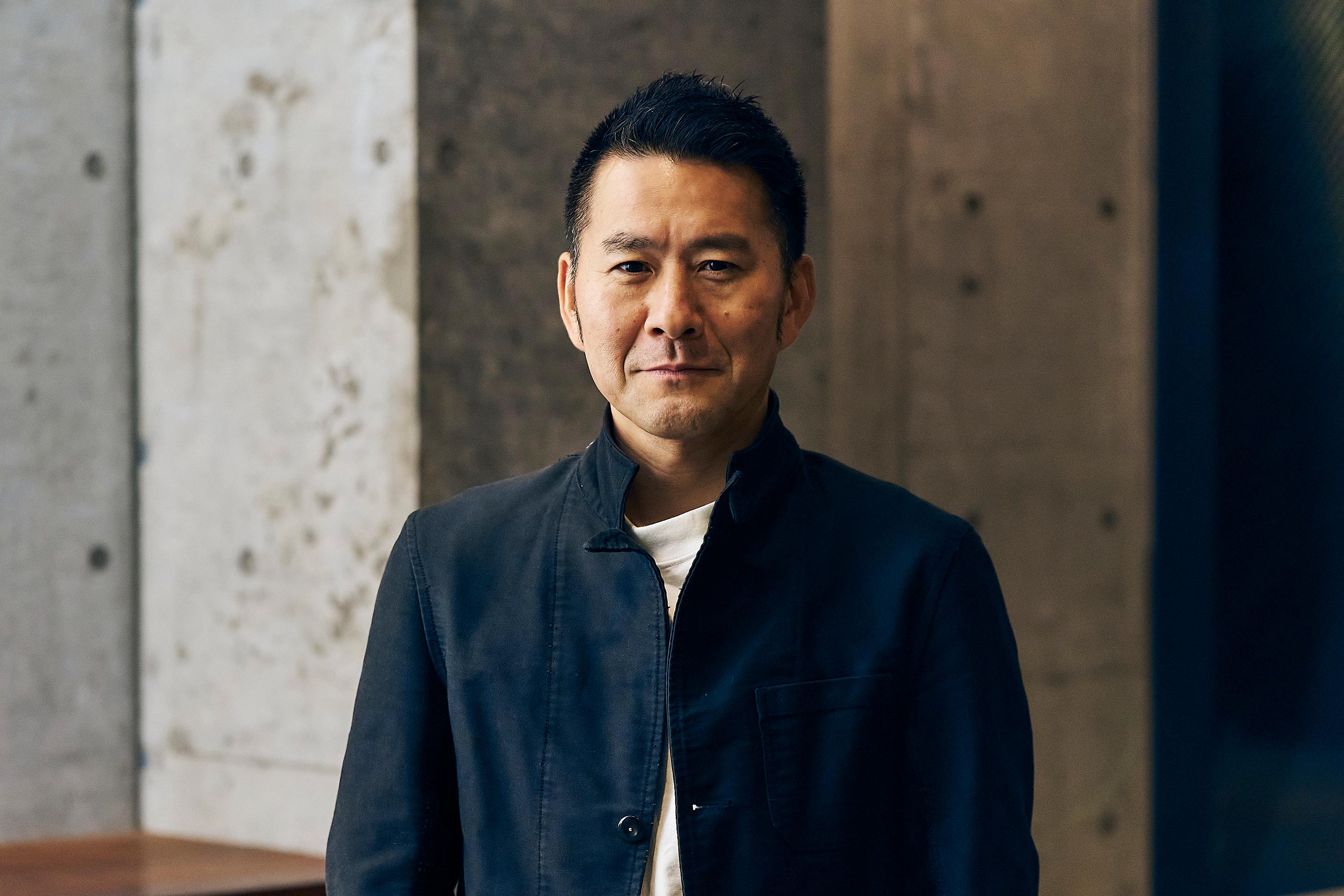ビジネスNEW
識者が断言、プログラミング学習に年齢制限がないワケ(後編)

前編では、Kari Kakkonen氏、鳥井 雪氏のそれぞれの著書について、どのような思いで執筆されたのか、子どもたちに興味を抱かせるためにちりばめた工夫などを語っていただきました。後編では、両氏が、絵本の制作とIT教育に携わる中で見えた課題感、そしてIT教育の未来展望について意見を交わします。
教師のITスキル不足が共通の課題
──フィンランドと日本、それぞれIT教育の現状はいかがでしょうか。
Kakkonen:フィンランドでは小学校1年生から高校生まで、算数や数学の時間の中で、プログラミング(コーディング)が必修になっています。残念ながらテスティングはカリキュラムに含まれていませんが。日本はどうでしょうか。
鳥井:日本では2020年度から、小学校でプログラミング教育が必修化されました。しかし、既存の授業の中で触れるにとどまり、プログラミングの科目が独立したわけではありません。プログラミングを特別なものとしてではなく、日常の中で触れるという点ではいいのですが、(プログラミングに対するスキルなどのばらつきもあり)教える側が戸惑っているのを感じます。

Kakkonen:フィンランドの教育現場も似たような状況です。学年が上がるにつれて、少しずつ教科書のボリュームが増えて、最終的には数学の教科書のうち、1章がプログラミングの内容に割かれます。そのため、数学の先生はプログラミングの先生にもならなければなりません。しかし、必ずしも全ての先生がプログラミングができるわけではないのが、共通の課題と言えるでしょう。
そういう意味では、鳥井さんが取り組んでいるNPO「Waffle」の活動の重要性が分かりました。フィンランドでは、ボランティアやNPOといったいくつかの組織が、授業のサポートに入る活動をしています。
鳥井:私は先日、AI時代の情報教育を議論する国際会議「Asia Pacific Computer Education Conference 2024」に参加してきたのですが、やはりどの国でも教師を育てることは難しいという声が聞かれました。国語や数学などと違って、大人たちが習ってこなかったことを教えるため、IT教育は今、過渡期にあると思っています。
Kariさんは教師向け副教材として、『Dragons Out!』の各国語版のプレゼンテーションを無償で配布されています(*)。とても素晴らしい取り組みだと思います。
このように、業界に関わっている人が、教育をサポートするがわに回るような活動の必要性が高まっているように思います。
*フィンランド語、英語の他、全22言語のプレゼンテーションが公開されている(2025年3月時点)
参考: https://www.dragonsout.com/p/presentation-for-teachers.html
プログラミング学習は社会との接点に成り得る
Kakkonen:教育方針に関して、プロのプログラマーやテスターを養成するには、どのようなパスがいいと思いますか? 7、8歳から関心を持つように教え、小さいときから学ぶのか。あるいは、もう少し中学、高校辺りから触れて、大学になってからしっかり学ぶのが良いのか。鳥井さんはどう考えていらっしゃいますか。
鳥井:私はどちらのパスでも大丈夫だと思います。私がプログラミングを始めたのは、社会人になって24、5歳くらいの頃です。当時、コンピューターのことは何も知りませんでした。
ただ、いずれにせよ大事なのは、コンピューターやプログラミングの世界と、自分の世界が全く関係のないものだという感覚を持たせないことです。小さいうちから「自分が働きかければ、何かを作り出せるものとしてコンピューターがある」と知ってもらえれば、その子が必要とする時期に、活動を始められると考えています。
Kakkonen:私も同じ意見です。私たちの本を読んで、子どもたちがプログラミングに対する見方やマインドセットが変わって、コンピューターやプログラミングについて学びたい、あるいは使ってみたい、敵ではなくて味方、友だちなのだというふうに考えてくれたら、とてもうれしいですね。

──ある脳科学者によると、プログラマーが使う脳の領域は、哲学者が使う脳の領域と同じだと言います。プログラマーやテスターに全く向いていない人は心を病んでしまうのは、そのためだとも聞きます。こうした向き不向きは、ミュージシャンやアスリートと同じような適性があるのでしょうね。お二人はどう思われますか。
Kakkonen:クリエイティビティー、ロジックというレベルにおいては、誰しもその才能があると思います。そして働きかけさえあれば、どの子どもも、やってみたいと思うものではないでしょうか。
才能の成長度合いに差はあれ、トライしてみるという意味では、チャンスは全ての子どもに開かれています。
鳥井:私も同意です。全ての子どもにチャンスが開かれているべきだと考えています。試さないとその子の関心や才能は分からないからです。今は残念ながら、そうではありません。プログラミングの必修化を通して、できるだけ多くの子どもたちの体験が増えることを期待します。
また、プログラミングを学ぶに当たって、子どもたちがプログラミングをより良く学ぶ段階を体系化できていないように思いますので、そこに改善の余地があると考えています。
それに、プログラミングを学んで、プログラマーやテスターになるだけが全てではありません。技術者と会話するための基礎知識を持つことや、今や社会に欠かせないコンピューターを接点に、自身が社会の一構成員である感覚を持つことは、社会人としても大事な能力の一つだと思います。
Kakkonen:本当におっしゃる通りだと思います。まさに鳥井さんが先ほどご自身もそうだとおっしゃっていましたし、私も大人向けのテスターのトレーニングをたくさんやってきました。これまでに300人ほど、いわゆる非IT人材だった方を、IT人材に転換し、彼らのキャリアチェンジをサポートしてきました。大人になってもプログラミングを学ぶのは十分可能です。ただ、やりたいという意思があるかどうかが重要でしょう。
鳥井:思い込みや偏見によって、自分には縁のない世界だと思わないような状況が整えられるといいですよね。
多様性に開かれつつあるプログラミングへの世界
Kakkonen:フィンランドにはウィメンコード(フィンランド名:Mimmit Koodaa program)という団体があり、男性だけでなく、女性の成功例としてのお手本がたくさんあります。場合によっては女性の方がプログラマーの適性が高いこともあるでしょう。
鳥井:そうですね。世の中にはいろいろな子どもがいるので、自分もそうなれるのだと、想像してもらうためにも、性別や国籍に関係なくさまざまな人がITの世界に関わっていることを示せるのがいいですね。
Kakkonen:多様な子どもたちがいる観点では、例えば自閉症スペクトラムの方は、非常にテスターに向いているという事例があります。そういった多様性の観点を次回の本で盛り込むかもしれません。
鳥井:私も自著の中で多様性を十分に盛り込めたかというと、そうではありませんが、例えばイラストで、同じような体形に偏らないように気を付けました。
『Dragons Out!』はファンタジーなので、現実の自分を離れてストーリーの世界に没頭できます。そういった意味で、ダイバーシティーを受け入れる余地が広いのではないかと感じました。
Kakkonen:そうですね、ファンタジーの世界では、何でも可能になります。ですから、今の社会よりも、こうあるべきという社会を描き、それを伝える責任も感じています。ダイバーシティーの観点においても、今より一歩進んだ世界を、物語の中で描けると思うのです。
鳥井:全くその通りですね。
AI時代におけるIT教育の展望
──昨今、生成AIをはじめとして、ソフトウェア開発のバックグラウンドが大きく変わってきています。そういった中でお二人がこれから、どのような教育を目指されるのか、お聞かせいただけますか。
鳥井:どうプログラミングを書くかは、すでにAIがサポートしてくれるレベルに達しています。ですが、そのコードは本当に私たちが表現したかったものなのか、最終的な判断は、依然として人間が行う必要があり、今後も私たちに委ねられている領域であるはずです。
そして、AIができないこと、つまり世に出すべきプロダクトについて責任を持ち、責任を持つための判断には何が必要かを考えられるーーそのためのプログラミング教育をしていきたいです。
生成AIにも言及がありました。生成AIはAI自体のデータセットによる偏りが生じる問題も抱えています。AIに対する正しい知識を持ち、適切に評価できるような教育も、今後は含まれていくでしょう。
Kakkonen:私も同じ考えです。AIはテスターにとっても便利なものですが、あくまでツールであって、人を代替するものではないと考えています。確かにAIを使えば、テストコードを作るスピードは向上しますし、テストケースのアイデアを人間より早く出すこともできます。しかし鳥井さんがおっしゃったように、最終的な結果に責任を持つのは人間です。
また、偏りについて言及されていましたが、意識的にAIを使うためには、企業であろうと、学校であろうと、AIの活用方法のポリシーを決め、明文化しておくことが必要です。そうでなければ、悪用を避け、公正で適正に利用をすることが担保できないからです。
『Dragons Out!』が出版された時はAIがここまで発展していないタイミングでしたので、本の中では少し触れるだけにとどまっています。今後、続編を書く際は、AIはとてもパワフルなツールですので、一緒に戦ってほしいスーパー騎士のようなキャラクターで登場することになると思います。
鳥井:『ユウと魔法のプログラミング・ノート』は生成AIが急激に普及し始める直前くらいの時期に出版しました。ですが、作中に出てくる魔法のプログラミング・ノートは、物語で今のAIと同じような役割を果たしています。もし私が続編を書くとすれば、ノートブックに生成AIに似た強さを表現したり、AIの危険性などにも触れたりするのではないかと思います。
Kakkonen:実は『ユウと魔法のプログラミング・ノート』のあらすじを聞いて、生成AIっぽいなと感じていました。イアン・バンクス氏などが手がけるSFの世界では、全ての人にAIヘルパーがいるような未来が描かれています。もしかしたら鳥井さんの参考になるかもしれませんね。
学び続けるその先へ
──最後に、「HQW!」 の読者へメッセージをお願いします。

Kakkonen:皆さんに、ずっと学び続けてほしいと思います。それがプログラミングであろうと、テストであろうと、生成AIだろうと、常に新しく学ぶことはありますし、学び続けるマインドを持ち続けてほしいです。Arigato Gozaimasu!
鳥井:このメディアの読者は新しいことに興味・関心がかなり高い人だと思うのですが、学び続けることで広がり続ける世界がありますよね。私自身も学び続けたいですし、新しいことに関心を持ち続けて、皆さんにもこの世界を楽しんでほしいです。
この記事は面白かったですか?
今後の改善の参考にさせていただきます!






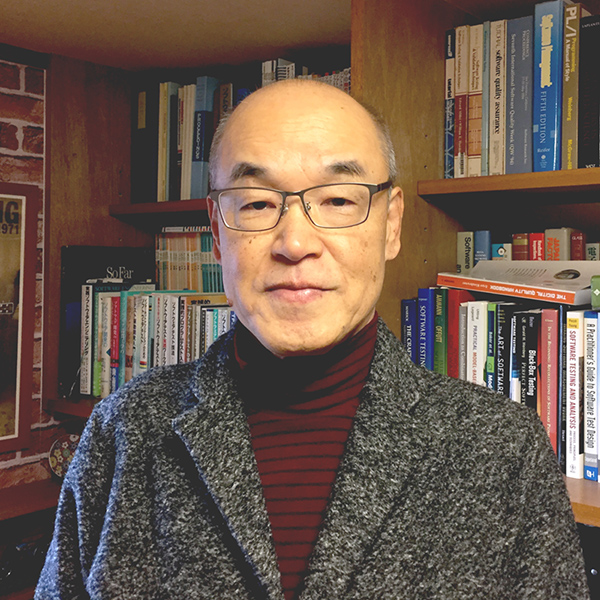




















.png)